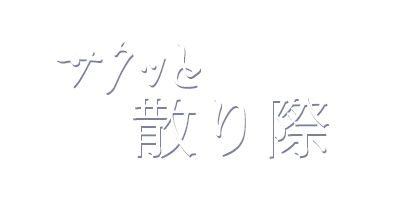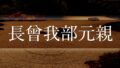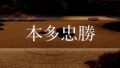江戸幕府が豊臣家を滅ぼした「大坂の陣」。
この戦いでは、真田信繁など華々しく散っていった武将が有名です。
一方で、情けない失態を犯した武将もいます。
それが「薄田兼相」です。
彼は「女遊びの間に砦を落とされる」というしくじりをしてしまったのです。
そんな薄田兼相の晩年や最期はどんなものだったのでしょうか。
「薄田兼相」とは?簡単に説明
薄田兼相は生年や生まれた場所は不明で、豊臣秀吉の馬廻衆として豊臣家に仕えたということ以外、前半生はよく分かっていません。
(講談などによる伝承はありますが、それは後述します)
「薄田兼相」の晩年
1614年(慶長19年)、豊臣方として大坂の陣に参戦しました。
冬の陣で、薄田兼相は博労ヶ淵砦(現在の大阪市西区にある西長堀駅周辺)の守備を任されます。
このとき、薄田兼相は後世に語り継がれる生涯最大のしくじりをしてしまうのです。
博労ヶ淵砦の戦い
幕府軍の約5000人が砦に攻めかかります。
豊臣方は約700人と少人数でしたが、最初は有利に戦いを進めていました。
博労淵砦を落とさないと大阪城へ近づけない幕府軍は、懸命に砦を攻めます。
すると、急にあっさりと砦が落ちてしまったのです。
砦の兵たちは必死に戦っていたのですが、途中から大きく士気が落ち、逃げる者まで出てきました。
指揮官である薄田兼相が不在だったからです。
なんと彼は、戦いの前夜に砦を抜け出し、遊郭で女遊びをしていたのです。
遊郭にいる間に戦いが始まり、砦は落ちてしまいました。
橙武者
大阪城に戻った薄田兼相へは、味方から白い目を向けられます。
やがて「橙武者(だいだいむしゃ)」と揶揄されるようになりました。
橙武者は「見た目だけ立派で役に立たない見かけ倒し」という意味で使われました。
当時、橙は「色は鮮やかで見事だが、酸味が強くて食べられず、正月飾りくらいにしか使えない」とされていたのです。
このことから、薄田兼相は見事な体格だったことが分かります。
とは言え、とんでもない失敗をしたことには変わりありません。
「薄田兼相」の死に様
大坂冬の陣は、幕府軍が大幅に有利な条件で講和しました。
しかし、1615年(慶長20年)に夏の陣が始まります。
薄田兼相は変わらず豊臣方に属しており、夏の陣に参戦しました。
この夏の陣で、彼は幕府軍を相手に奮戦した後、戦死しました。
「薄田兼相」の死に様の信憑性
彼の死に様については「難波戦記」という軍記に書かれています。
難波戦記は、書かれた年代が不明で誤りも見られることから、史料としての信憑性は高くありません。
しかし、大阪府羽曳野市に薄田兼相の墓があることや、大坂の陣以降、彼に関しての記録が特に無いことから、大坂の陣で死んだ可能性が高いと思われます。
「薄田兼相」の小ネタ
前半生が不明な薄田兼相ですが、講談や歌舞伎などの題材となった豪傑「岩見重太郎」と同一人物だという説があります。
岩見重太郎は、若い頃に諸国を巡って武芸を磨き、1615年に大坂の陣で戦死したとされています。
しかし「薄田兼相=岩見重太郎」であることや、岩見重太郎が実在していた、あるいは、講談などで語られるような豪傑だったことを示す信憑性の高い史料は見つかっていません。
まとめ
薄田兼相の晩年や最期について紹介しました。
薄田兼相については史料が少ない上に、民間伝承も多く、よく分からない部分が多いというのが実際のところです。
しかし、大坂の陣でのしくじりにより、現代まで名を残すこととなりました。
このしくじりが無ければ、彼が歴史に名を残すことは無かったかもしれません。
反面教師のお手本のような人物です。